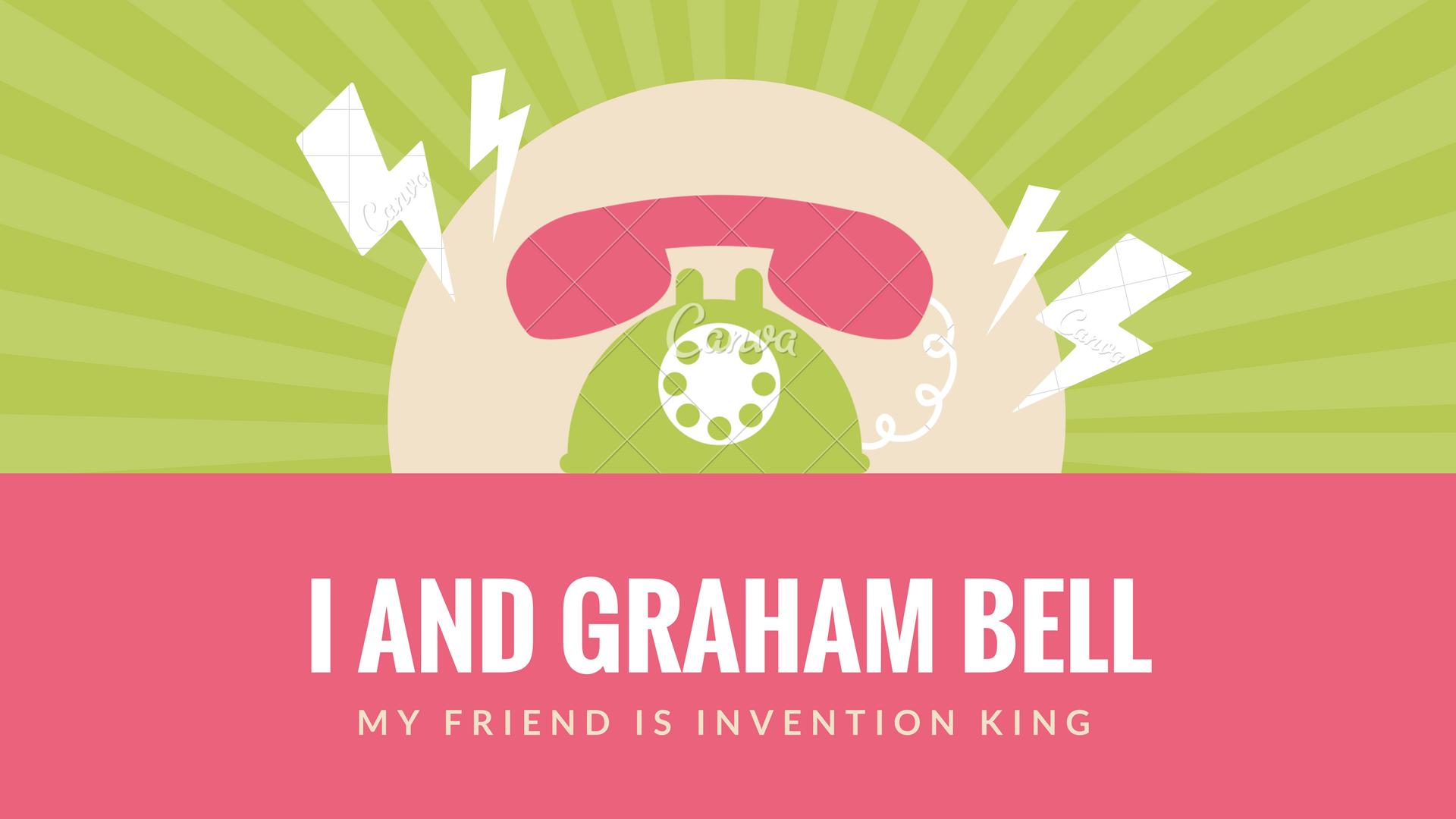目次
あらすじ
1939年。少女は6歳でホロコーストの魔手にかかった。
1945年。彼女は12歳でホロコーストから生き延びた。
奪われた平和な生活と、長い過酷な日々。
著者の記憶に残る「ユダヤ人絶滅計画」。
読書感想文(2000字、原稿用紙5枚)
ナチス・ドイツによる「ユダヤ人絶滅計画」は、ほんとうに20世紀のできごとだったのかと疑ってしまうくらい、残虐で極悪非道で凄惨な行いであると私は思います。
<これは物語ではなく、写真をならべたアルバムのようなものです。
でも記憶から抜けおちてしまったり、黄ばんでしまったものもあるので、これから先のページには、いまもくっきりしているものだけを選びました。>
本書はノンフィクションです。著者・フランシーヌが実際に経験したとされることが書き表されています。
彼女はユダヤ人でありながら「戦争捕虜妻子」という身分にあり、国際条約の保護下にありました。だから強制収容所に入れられながらも生き延びることができたのです。
強制収容所。漢字を並べただけでおぞましい印象を受ける施設です。代表的なのは現在のポーランドにある「アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所」です。世界遺産となっていて、何度か映像を目にしたことがあるのですが、私はその光景にいつも何も言えなくなります。
第二次世界大戦の戦争当時、彼女は10歳くらいの子どもでした。
私は自分の10歳ころの記憶はすでにおぼろげですが、フランシーヌは彼女自身が体験したことをはっきりと細かく詳細に記述しています。
強烈な体験はそれだけ脳みそに焼き付くというか、忘れたくても忘れられないというか、繰り返し思い出さざるを得ないというか、戦争が残した爪痕は遺跡だけではなく人間の心にも表れるのだな、と思いました。
<これは「文学」というものでもありません。
ただわたしは、まるで魂の砂漠にいたようだった戦争中のつらい思い出を、生きのこった者として証言しなくてはならないと思い、12歳のころから、よみがえってくる記憶をあれこれ書きとめつづけていました。>
フランシーヌはつらい思い出が「よみがえってくる」と表現しています。
語り口がドライかつ客観的かつ淡々としているため、臨場感たっぷりに悲壮感を出しているわけではありませんが、それでもなお、文章を裏打ちしている彼女の感情がわずかながら読み取れるような気がします。
<そういうわけで、この本は、わたしの頭のなかにずっとあったもの。
1967年、それをようやく取りだし、実際に文字にして、思っていたことや考えていたこと、書きためていたことを、何週間かかけてまとめたものです。>
1967年ということは、終戦の日から20年以上経過しています。10代の少女だった彼女は、30代半ばとなりました。
<収容所にいた者はだれも、そこから完全にもどれはしないのだ。>
フランシーヌはこのように書き残しています。
「圧倒的な地獄」と呼んでも差し支えないような過去を、残酷が空気中に漂っていた過去を、二度と思い出したくないであろう過去を、どうにかして文章として起こさなければならない。
そのような「逃れられない運命」のような何かを、彼女はずっと感じて生きてきたのだろうと推測します。
ユダヤ人を「絶滅」させることに特化した収容所にありながら、捕虜の妻子として「特別に」絶滅から逃れられたフランシーヌの内面には、いつも大きな影がさしていたのだろうと想像します。
強制労働、銃殺、ガス室、人体実験。
「狩られてきた」ユダヤ人が虐殺されていく光景を、少女はほんとうはどんな思いで見ていたのでしょうか。
本書の邦題は『いのちは贈りもの』ですが、その考えにのっとれば、贈りものを大切に扱わない理由ありません。それがユダヤの神からのものであるか、キリストの神からのものであるかに関わらず。
命は平等ではないと私は思いますが、平等ではないからこそ、平等にしていこうとする努力こそが人間的な営みであると強く思います。
(1531字、原稿用紙4枚と8行)
おわりに
フランシーヌ・クリストフ(河野万里子訳)『いのちは贈りもの』を含む「2018年読書感想文課題図書のまとめ」はこちら
そのほかの「読書感想文」はこちらから。